この記事は、実際に各校の説明会に参加し、養成課程を修了した私が「首都圏で通える中小企業診断士 養成課程」を比較したメモです。
養成課程はいくつか選択肢があるものの、仕事を続けながら通う前提だと「現実的に通える学校」が限られます。
そこで本記事では、学校ごとの“違い”が見えやすいように、説明会で感じた特徴と、選び方の軸を先に整理します。
※カリキュラムや募集条件は年度で変わる可能性があるため、最終判断は必ず各校の公式案内も確認してください。
この記事でわかること
・首都圏で通いやすい養成課程(大学院/専門校)の違い
・4校(日本マンパワー/東洋大学/城西国際大学/千葉商科大学)の特徴
・説明会で見ておくべきポイント(学校選びの基準)
・「自分に合う1校」を決めるための考え方
結論:学校選びは「休める時間」と「研究の重さ」でほぼ決まる
私の体感では、首都圏の養成課程選びはこの2軸で迷いが減ります。
- 平日夜に時間が取れるか(夜間+休日型が合うか)
- 研究(論文・研究計画)にどこまで力を入れたいか(大学院の色が強いか)
この2つを先に決めると、比較が一気に楽になります。
候補の絞り込み(働きながら通う前提で現実的だった4校)
私は首都圏在住で、平日は少なくとも18時まで仕事がある前提でした。
その条件で通学の現実味があったのは、次の4つです。
・日本マンパワー(1年で修了、※大学院ではない)
・東洋大学(2年)
・城西国際大学(2年)
・千葉商科大学(2年)
一方で、私の条件では見送りました。
・昼間中心の授業がある学校(平日昼が難しい)※例えば、法政大学
・住み込み型・短期集中(生活の制約が大きい)※例えば、中小企業大学校
・自分の目的と優先順位に合わない特色が強い学校 ※例えば、日本生産本部
ここは人によって条件が変わるので、「自分が確実に出せる時間」から逆算するのが正解です。
4校比較の早見(体験ベースのざっくり)
細かい費用や所在地はパンフ・公式で確認できるので、ここでは“通い方”と“学校の色”に絞ります。
・最短で資格取得まで行きたい → 日本マンパワー
・研究も含めてしっかり学びたい → 東洋大学
・選考の情報が比較的オープン、雰囲気が柔らかい → 城西国際大学
・平日が厳しい人にとって現実的(休日中心の印象) → 千葉商科大学
各校の特徴(説明会で見えたこと)
日本マンパワーの特徴(1年・夜間+休日)
公式: https://www.nipponmanpower.co.jp/ps/choose/smemc_rtc/
最大の魅力は、働きながら「夜間+休日」で通えて、1年で完了できる点です。
説明会がリアル開催だったこともあり、実務実習で作るアウトプット(診断実習シートなど)を実物で見られたのが強烈に良かったです。ここは他校ではあまり見せてもらえない印象でした。
また、OBが質疑応答に出てくる時間があり、副業の現実や診断士ネットワークの話など、ネットに出づらい話が聞けたのも収穫でした。
一方で、選考(筆記・グループワーク)の中身については、説明会で深掘りしても情報は出づらい印象です。面接テーマや具体的な課題を取りに行く目的だと、期待しない方が良いです。
東洋大学の特徴(2年・研究の比重が重い)
公式: https://www.toyo.ac.jp/academics/gs/mba/finance/SME_TOP/
説明会で一番強く感じたのは、「養成課程でも研究はしっかりやる」という姿勢です。
同じ2年でも、研究(研究計画・論文)に時間を割く覚悟が必要な学校だと思います。
その分、研究計画書の書き方のアドバイスが具体的に得られる場面があり、説明会自体の価値は高いです。
「どうせやるなら、がっつり学びたい」「研究も含めて自分の軸を作りたい」という人には合います。
私は当時、研究にそこまで意味を見いだせず、最終的に別の選択肢を優先しました(ここは自身の価値観が判断基準です)。
城西国際大学の特徴(2年・雰囲気が柔らかく、質問に答えてくれる)
公式: https://www.jiu.ac.jp/graduate/management/smec/
説明会の空気がフランクで、過度な“アカデミックな堅さ”は感じませんでした(主観です)。
特徴として記憶に残っているのは、選考過程に関する質問にも比較的答えてくれる姿勢があったことです。
研究テーマについても、最初は仕事に近いテーマで入って、入学後に調整していけばいい、というニュアンスがあり、研究に対するハードルは相対的に低めに感じました。
説明会に出たら、遠慮せずに質問した方が得をするタイプの学校だと思います。
千葉商科大学の特徴(2年・休日中心で、平日が厳しい人に現実的)
公式: https://www.cuc.ac.jp/dpt_grad_sch/graduate_sch/master_prog/smec/index.html
休日中心に講義が組まれている印象で、平日に時間が取りにくい人にとって通学設計が現実的だと感じました。
説明会は事務的な話が中心になりやすい一方で、研究計画の相談が必要な人は別途、教授との1on1につながる動線がありました。
私も教授と話す機会があり、そのときの内容は別記事にまとめています。
この1on1は雰囲気は柔らかいのですが、同席の事務局の方がかなり丁寧にメモを取っていて、「任意だけど、実質は選考の一部として準備した方がいい」と感じました。
(教授面談の記事)
https://smec.blog/smec/yousei-chibashodai-mendan/
学校選びチェックリスト(5項目)
首都圏の養成課程は、学校名だけで比較すると迷います。先にこの5つを決めると、候補が自然に絞れます。
1)通学スタイル:平日夜は出せる?休日中心がいい?
- 平日夜も出せる(週2〜3回の夜間も可)
- 平日は厳しい(休日中心じゃないと続かない)
2)期間:最短で取りに行く?2年でじっくり?
- 1年で一気に終わらせたい
- 2年かけて無理なく積み上げたい
3)研究(研究計画・論文):どこまでやりたい?
- 研究も含めて、しっかり学びたい(論文も本気でやる)
- 研究は最低限でいい(実務・実習を重視したい)
4)説明会で重視するもの:何を取りに行く?
- 実際のアウトプットや、OBの生の話を聞きたい
- 選考や運用の具体(雰囲気・質問の答え方)を掴みたい
5)生活条件:2年間の継続に不安はある?
- 家族の理解/時間の確保/体力に自信がある
- どれかが不安(通学負担が重いと折れそう)
【簡易診断】この学校が合いやすい
チェックリストの答えが、どこに寄っているかで判断が早くなります。
- 「1年で終わらせたい」「夜間+休日で通いたい」「OBのリアルが欲しい」
→ 日本マンパワーを最優先で検討 - 「研究もしっかりやる覚悟がある」「研究計画書から鍛えたい」
→ 東洋大学が合いやすい(研究の比重を重く見積もって準備) - 「雰囲気が硬すぎない方が続く」「説明会で選考の質問も投げたい」
→ 城西国際大学を見に行く価値が高い(質問量がそのまま情報になる) - 「平日が本当に厳しい」「休日中心で現実的に回したい」「研究計画を1on1で詰めたい」
→ 千葉商科大学が有力(教授面談は“面談”として油断しない)
参考:養成課程の人数・年齢感(※2023年の雑誌掲載情報)
当時読んでいた雑誌『企業診断』(2023年)に、養成課程の人数や年齢感の記載がありました。最新値は変わる可能性があるので、あくまで雰囲気の参考としてメモを残します。
・中小企業大学校:平均年齢34歳(年代20〜50代)
・日本マンパワー:年代20〜50代
・法政大学:年代20〜60代
・兵庫県立大学:平均年齢40歳(年代20〜50代)
まとめ:迷ったら、まずこの順で決めると早い
- 週にどれだけ時間を出せるか(平日夜OK?休日だけ?)
- 研究の比重をどう捉えるか(研究もやりたい/最短で進めたい)
- 説明会で「続けられるイメージ」が持てたか(空気感・相性)
首都圏の養成課程は、スペック比較だけだと迷います。最後は「2年間(または1年)を現実に回せるか」で決まります。
👉次に読むなら、この2本が準備の順番として一番早いです。
・養成課程の倍率はどれくらい?目安と見方:https://smec.blog/smec/yousei-bairitsu/
・研究計画書の書き方(テンプレ+おすすめ本):https://smec.blog/smec/yousei-kenkyu-keikakusho/

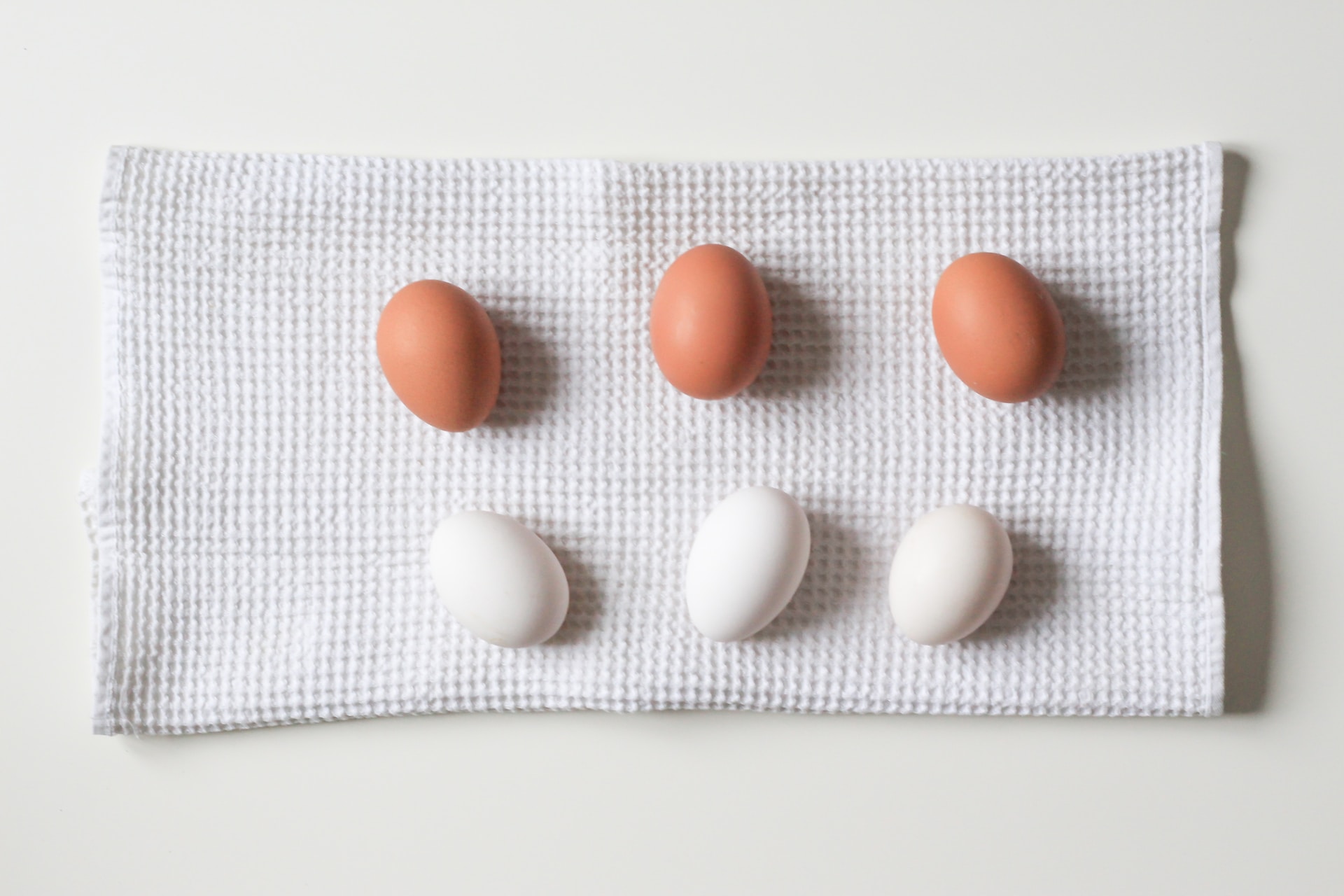
コメント