涙が止まらないほどの感動を味わいたい。穏やかで優しい物語に癒されたい。心が疲れたとき、寄り添ってくれるような小説を読みたい。
そんなあなたのために、「泣ける・感動・優しい」をキーワードに、心に響く名作を厳選しました。
大切な人との絆、喪失と再生、日常に潜む優しさ――。読後に余韻が残り、気持ちがじんわり温かくなるような作品を中心に、短編から長編まで、ジャンル別に幅広く紹介します。
通勤時の電車内や就寝前、きっとあなたの心を癒してくれる1冊が見つかるはずです。
涙が止まらない…「泣ける小説」の傑作たち
どうしようもなく心が沈むとき、そっと寄り添ってくれる物語があります。
ここでは、静かに涙を誘いながら、どこか心があたたかくなる「泣ける小説」を厳選しました。大切な人との別れ、家族の絆、命の重み。読後にはきっと、今を少しだけ大切にしたくなるはず。
やさしくて、泣けて、でも前を向ける。そんな一冊に出会えますように。
ナミヤ雑貨店の奇蹟(東野圭吾著)
空き家となった古い雑貨店に逃げ込んだ3人の青年たち。そこで彼らは、過去から届いた“悩み相談の手紙”と出会います。この雑貨店には、時を超えて悩みが届き、返事を出すことができる不思議な力があったのです。
戸惑いながらも返事を書き続ける3人は、看病と夢のどちらを選ぶか、音楽を諦めるべきかといった切実な悩みに向き合い、少しずつ心を変化させていきます。
バラバラに思えた短編がやがて一つの大きな物語へと繋がり、読後には温かな涙があふれます。
感動・泣ける・優しいがすべて詰まった、東野圭吾の傑作です。心が疲れたときにこそ読んでほしい一冊。
西の魔女が死んだ(梨木香歩著)
学校に行けなくなった少女・まいが、田舎に住む“西の魔女”こと大好きなおばあちゃんのもとで暮らすことに。魔女になるための修行は、「自分で決めること」を学ぶ毎日。家事や自然とのふれあいを通じて、少しずつ心を整え、前を向いていきます。
そっと寄り添うように見守るおばあちゃんの温かさ。静かな時間の中にある生と死、成長と別れ。ラストに訪れる出来事は、涙を誘いながらも、読者の心をあたたかく包み込んでくれます。
優しくて、静かに泣ける感動作。
心に寄り添ってくれるような1冊を探している方に、ぜひおすすめしたい名作です。
とんび(重松清著)
不器用ながらも一人息子を懸命に育てる父・ヤスの姿を描いた感動長編。妻を突然失い、男手ひとつで子どもを育てることになったヤス。昭和の町並みを舞台に、父と子の不器用な日々が、温かく、時に切なく綴られていきます。
父親としての喜び、迷い、葛藤、そして息子へのまっすぐな愛情。読み進めるほどに、ヤスの背中に込められた想いに心が締めつけられ、気づけば涙がこぼれているはずです。
子育て中の親なら胸に刺さる描写が満載で、読み終えたあとにはきっと家族に優しくなれる一冊。泣ける小説を探している人に、まっすぐおすすめできる作品です。
明日の記憶(荻原浩著)
働き盛りの主人公が突然、若年性認知症と診断される――。日常のなかで少しずつ記憶が抜け落ちていく不安や、自分の変化を隠そうとする切なさが胸に迫ります。仕事や家庭を守りたい一踏ん張る姿に、言葉にならない感情がこみ上げてきます。
重いテーマでありながら、物語はどこか静かで優しく、ラストには確かな光が差し込みます。現実味のある設定だからこそ、読後には多くのことを考えさせられる一冊です。
深く静かに心を打つ、記憶に残る小説。大切な人と過ごす“今”を大事にしたくなる物語です。
絶唱(湊かなえ著)
南国・トンガ王国を舞台に、異国の地で生きる人々の心の揺れを描いた短編集。湊かなえといえば「告白」などの“イヤミス”で知られていますが、本作ではその印象がやわらぎ、静かでじんわりと沁みる物語が展開されます。
それぞれの短編がわずかに繋がっていく構成は、過剰な仕掛けがなく、かといって淡白でもなく、ちょうどよい距離感。押しつけがましさのない語り口が、読者の心を自然と掴んで離しません。
重すぎず軽すぎず、そしてどこかあたたかさを感じる読後感。湊かなえの新たな一面に出会える一冊として、ミステリーに苦手意識がある方にも手に取ってほしい作品です。
夏の庭(湯本香樹実著)
「人が死ぬところを見てみたい」と興味本位で行動を始めた小学6年生の少年3人。近所のひとり暮らしの老人を観察するうちに、思いがけず本人に見つかってしまいます。そこから始まった奇妙な交流は、やがて本物の人間関係へと変わっていきます。
最初は距離のあった子どもたちと老人の間に少しずつ生まれていく信頼。言葉少なな時間の中に流れる優しさと孤独。そして夏の終わりに訪れる別れの場面は、静かに、でも確かに心を打ちます。
子ども向けと思って読んでいたはずが、大人ほど深く響く場面がある。命や別れについて、やわらかく、でもまっすぐに向き合わせてくれる一冊です。
ライオンのおやつ(小川糸著)
30歳を過ぎて余命を宣告された主人公が、静かな瀬戸内の島にあるホスピス「ライオンの家」で残された時間を過ごす物語。海風と光に包まれたその場所には、穏やかに生きようとする人々が集い、日々を慈しむように暮らしています。
なぜかいつもメイド服を着ている院長、ワインづくりに励む若者、支えてくれる家族や島の人々。それぞれのエピソードが優しく心にしみてきて、気づけば涙がこぼれてしまう。けれど、どこか温かく、悲しみに沈むことはありません。
命と向き合うことを、こんなにも柔らかく描けるのかと思わせてくれる一冊。大切な人との時間を改めて見つめ直したくなる、読後にやさしさが残る物語です。
キャロリング(有川浩著)
物語は、主人公が銃口を向けられる衝撃的な場面から始まります。一見するとサスペンス小説のようにも感じられますが、読み進めるうちに浮かび上がるのは、人と人との関係のあたたかさ。家族や恋人、子どもたちとのすれ違いや再生が、優しく丁寧に描かれていきます。
舞台はクリスマスシーズン。タイトルにもなっている「キャロリング」は、教会の人々が街に歌を届ける風習に由来し、作品全体に穏やかな空気をもたらします。
優しさだけでなく、痛みや葛藤にも真っ直ぐに向き合い、登場人物それぞれが自分の意志で前に進んでいく姿が印象的です。静かに胸に響く、少しだけ強くなれるような物語です。
静かに心が震える「感動の物語」
派手な展開や大げさな演出がなくても、なぜか心の奥深くに響いてくる物語があります。
そんな“静かな感動”をもたらしてくれる小説を集めました。登場人物たちの小さな勇気や、誰かへの思いやりが、読者の心にもやさしく沁みてきます。
ひと息つきたいとき、そっと背中を押してほしいときに。静かに、でも確かに、心を震わせてくれる一冊と出会えますように。
神様からひと言(荻原浩著)
主人公が配属されたのは、社内でも厄介者扱いのカスタマーリレーション部門。クレーム対応に追われる日々の中で、くせ者ぞろいの同僚たちとの騒がしくもどこか温かいやりとりが描かれていきます。
理不尽な上司、クセが強すぎる同僚、部下とのギクシャクした関係。会社員なら誰もが共感せずにはいられない日常が、ユーモアたっぷりに語られながら、いつの間にか心を打つ展開へとつながっていきます。
笑って、泣けて、少し前向きになれる。職場で悩んでいる人や、自分の居場所に迷いがある人に、そっと寄り添ってくれるような一冊です。
椿山課長の七日間(浅田次郎著)
長年、家族のために身を粉にして働いてきた椿山課長。ようやく昇進した矢先、彼は過労で命を落としてしまいます。けれど、どうしてもこの世に未練が残った彼には、七日間だけ現世に戻るチャンスが与えられます。しかも借りる体は、美しい女性のもの。
同じく短い時間だけ戻ってきた小さな少年とともに、二人のささやかな旅が始まります。すでに手放してしまったはずの家族や日常に触れながら、少しずつ心の奥にある想いが浮かび上がってきます。
切なくて、やさしくて、泣けるけれど、どこかあたたかい。読み終えたあとに、残された人と自分自身の「今」を大切にしたくなる物語です。
八月の銀の雪(伊与原新著)
静かな読後感と、じんわりと心が温まるような余韻を届けてくれる短編集です。登場するのは、仕事に疲れたり、人生につまずいたりしている普通の人たち。そんな彼らが、ふとした出会いや偶然をきっかけに、少しずつ前を向いて歩き出す姿が描かれています。
気球爆弾、深海魚、南極観測――それぞれの物語にさりげなく散りばめられた科学や歴史の雑学が、物語の背景に深みを与え、読み手の好奇心も刺激してくれます。
どの話もやさしさにあふれ、ほろりと涙がこぼれることもしばしば。1編ごとに読み切れるので、通勤や就寝前にもぴったりです。疲れた心にそっと寄り添ってくれるような一冊です。
ギフト(原田マハ著)
アートや風景に心を重ねながら、人と人とのやさしいつながりを描く短編集。原田マハならではの柔らかなまなざしで、恋やプロポーズ、家族の思い出といった日常の一瞬が、美しく描かれています。
収録された5編はどれも、淡くやさしい余韻を残す物語ばかり。なかでも「コスモス畑を横切って」は、お台場の景色とともに綴られる記憶の断片が胸を打ち、ふと過去の風景と気持ちが重なるような読後感を与えてくれます。
何かに疲れたとき、そっと開きたくなる短編集。優しさが沁みる一冊を探している方におすすめです。
お帰りキネマの神様(原田マハ著)
映画『キネマの神様』にインスパイアされた原田マハが、自らの原作世界をもう一度小説として紡ぎなおした一冊。物語は、人生の終盤に差しかかった登場人物たちが、もう一度夢に向かって歩き出す姿をやさしく描いていきます。
70歳を超えても挑戦をやめない人々の姿に、家族や友情の温もりが重なって、ページをめくるたびに心がふわっとあたたまる。現実の苦しさや寂しさを知っている大人にこそ響く場面が詰まっています。
疲れたときや、少し前を向きたいときに。物語の世界に身をゆだねることで、そっと背中を押してもらえるような一冊です。
舟を編む(三浦しをん)
一冊の辞書を編みあげていく人々の物語。地味で目立たないけれど、誰かの役に立つ言葉を届けるために、膨大な時間と情熱を注ぐ――そんな世界が丁寧に、ユーモアも交えながら描かれています。
主人公のまっすぐな性格や、並々ならぬ集中力はときに狂気にも近く、支える仲間たちとの絆や衝突もまた胸に残ります。気がつけば、読者自身も辞書づくりの一員になったかのような没入感があります。
読書が好きな人、言葉に惹かれる人にはたまらない一冊。何かに夢中になれることの尊さや、その姿がもつ静かな美しさを、そっと教えてくれる物語です。
ファミレス(重松清著)
いつ離婚を切り出されるかと内心怯えている、中年の“料理好きなおじさんたち”が主人公。それぞれが抱える家庭や人生の課題に向き合いながら、週に一度ファミレスで集い、言葉少なに過ごす時間が描かれます。
家族、夫婦、友情。年齢を重ねたからこそ向き合わなければならないテーマが、押しつけがましくなく、それでいて心にしっかり残るような形で描かれています。静かに進んでいく物語の中で、ふと胸に刺さるセリフや場面に出会えるのが重松作品らしさ。
温かさと切なさが交差する一冊。50代になって読み返すと、より深く沁みてくるかもしれません。
生きるぼくら(原田マハ著)
人生につまずいた青年が、長く疎遠だった祖母のもとを訪ね、田舎町で新たな一歩を踏み出すまでを描いた物語。祖母は認知症を患っているものの、時おりはっとするような言葉を口にする場面があり、そのひとつひとつに心を動かされます。
主人公自身も引きこもりの状態から少しずつ日常を取り戻していくなかで、人との関わりの大切さや、暮らしのリズムの温かさが自然と描かれていきます。派手な展開はなくとも、読後にはしっかりとした希望が残ります。
やさしい気持ちになりたいとき、ちょっと立ち止まりたいときに手に取りたくなる一冊。静かな時間をともに過ごすような読書体験が味わえます。
赤と青とエスキース(青山美智子著)
留学生のレイと、画材屋で働く青年ブー。ふたりを中心に、「絵」を通じて描かれる人々の物語が、時を超えて静かにつながっていきます。ひとつひとつの短編が独立しながらも、読み進めるごとに伏線が回収され、ラストには大きな感動が押し寄せます。
やさしさに満ちた言葉と出来事が、傷ついた心をそっと包み込んでくれるような一冊。読むタイミングによって、まったく違う気づきをくれる作品でもあります。
2022年本屋大賞第2位という評価もうなずける、温もりと構成の巧さが光る短編集。元気が出ないときや、静かに涙を流したい夜にそっと開いてみてください。
あかね空(山本一力著)
江戸の町を舞台に、京からやってきた豆腐職人とその家族の姿を描いた人情時代小説。丁寧に描かれる暮らしの風景や、登場人物の不器用ながらまっすぐな思いが、読んでいてじんわりと胸に沁みてきます。
苦難にぶつかりながらも、家族や仲間との絆を信じ、少しずつ道を切り開いていく姿は、静かな感動と勇気を与えてくれます。物語の語り口は軽やかで読みやすく、読後にはふわっと温かな気持ちが残ります。
家族や信頼といった、変わらない大切なものを描いた一冊。時代小説が苦手な方にも手に取ってほしい、やさしくて力強い物語です。
読後にやさしさが広がる「癒しの小説」
ちょっと疲れた日や、何も考えず心をほぐしたいときに。
やさしい登場人物や、穏やかな時間が描かれた小説を読むと、ほんの少し前向きになれることがあります。
このカテゴリーでは、読後にじんわりとあたたかさが残る「癒しの物語」を集めました。
日常の中にやさしさを見つけたくなる、そんな1冊と出会えるはずです。
スロウハイツの神様(辻村深月著)
脚本家の環を中心に、作家や写真家などのクリエイティブな若者たちが共同生活を送る“スロウハイツ”。穏やかで心地よい時間が流れるその場所に、新たな入居者がやってきたことをきっかけに、少しずつ人間関係が揺れ始めます。
日々のやりとりのなかにある静かな感情の重なり、居場所を見つけようとするもどかしさや優しさ。そして終盤、ゆったりと積み上げられた物語が伏線を回収しながら一気に展開していくラストには、驚きと深い感動が待っています。
やさしく、繊細で、登場人物のひとりひとりに心が動く。ミステリーの要素を含みながらも、読後にはあたたかい余韻が残る一冊です。
本日は、お日柄もよく(原田マハ著)
偶然出席した結婚式でのスピーチに心を打たれたことをきっかけに、主人公はスピーチライターという未知の世界へ足を踏み入れます。言葉が人の心を動かす力を持っていることを、実感として教えてくれる物語です。
スピーチの技術だけでなく、黙ること、待つこと、相手の心を受け止めることの大切さが丁寧に描かれ、静かに自分を見つめ直すきっかけをくれます。表題のスピーチ場面には、自然と涙がこぼれる読者も多いはず。
何度も読み返したくなる、やさしさと力強さを持つ一冊。落ち込んだときや背中を押してほしいとき、きっとあなたの言葉にも力を与えてくれる本です。
博士の愛した数式(小川洋子著)
交通事故の後遺症で、80分しか記憶を保てなくなった元数学者の「博士」。彼のもとに新しく派遣された家政婦と、その息子ルートとの交流を描いた、静かであたたかな物語です。
会うたびに記憶を失っている博士は、数式の美しさへの情熱だけは変わりません。家政婦の「私」と博士、そして息子との日常が少しずつ重なり合い、小さな信頼と優しさが築かれていきます。
数式が語るのは、冷たい論理ではなく、人と人をつなぐ思いやりや奇跡のような瞬間。涙を誘う物語というより、心が静かに癒されるような読後感が残ります。静かに寄り添ってくれるような物語を求めている人にぴったりの一冊です。
大事なことほど小声でささやく(森沢明夫著)
小さなバーを舞台に、悩みを抱えた人々がふと立ち寄り、心がほどけていく様子を描いた連作短編集。マッチョで陽気なマスターと、童顔の美人バーテンダー、そして艶やかな黒猫が迎えてくれる店には、どこか懐かしさと安心感があります。
登場するのは、日常に疲れた会社員や孤独を抱える歯科医など、どこにでもいるような人たち。彼らが語り、飲み、笑い、涙を流すなかで、それぞれの人生が少しずつ動き始めます。なかでも第四話は、過去を抱えた人物の心の奥にそっと触れるようなエピソードで、静かに胸に残ります。
読んだあと、ほんの少し優しくなれる。そんなあたたかな時間を与えてくれる一冊です。
月まで三キロ(伊与原新著)
科学的なまなざしと、人の心に寄り添うやさしさが絶妙に溶け合った短編集。日々の暮らしに少し疲れてしまった人たちが、それぞれの悩みや痛みを抱えながらも、思いがけない出会いや出来事を通じて少しずつ前に進んでいく物語です。
決まった定食しか頼まない女性、恋愛も結婚もあきらめた女性、受験を控えた少年、過去を手放せない叔父、そして、人生のすべてに絶望してしまった中年男性――どのエピソードにも、さりげない優しさと小さな希望が丁寧に描かれています。
難しいことは何も起こらないのに、読後にはじんわりと心があたたかくなるような一冊。
猫のお告げは樹の下で(青山美智子著)
人生につまずいたとき、不思議な言葉がふと背中を押してくれることがある。温かな奇跡を描いた、やさしさにあふれる連作短編集です。
舞台は、とある神社。運がよければ授かるという“葉っぱに書かれたミクジ”には、「マンナカ」「タネマキ」「タマタマ」など、ひと言だけの謎めいたメッセージが。けれどそれが、迷いや悩みを抱える人々の心にじわりと染み込み、思いもよらない変化をもたらしていきます。
物語は短編ごとに主人公が変わりながらも、少しずつ繋がっていく構成。登場する人々の優しさや気づきに、読み手もそっと救われていきます。青山美智子さんらしい、心がふっと軽くなるような一冊です。
鎌倉うずまき案内所(青山美智子著)
小さな案内所を舞台に、時を超えて紡がれる人々の物語。それぞれの短編は一見独立しているようで、少しずつ繋がり合い、最後にはひとつの世界が立ち上がります。
「木曜日にはココアを」にも通じる、やさしさと静かな余韻が漂う構成ながら、本作ではさらに“時間”という要素が加わり、過去と未来がゆるやかに交差していきます。物語の終盤には登場人物たちの関係性を整理する“年表”が用意されており、それをたどることで読後の楽しみが深まります。
すぐに理解できなくても大丈夫。少しずつ心に積もっていく言葉のかけらが、読み終えたあと、あたたかな記憶として残る作品です。
木曜日にはココアを(青山美智子著)
街の片隅にある小さなカフェを起点に、さまざまな人の人生が静かに繋がっていく連作短編集。自分では気づかないような小さな行動が、どこか遠くの誰かの背中をそっと押していたかもしれない――そんな優しい視点に心がほどけていきます。
物語は一話ごとに主人公が変わり、それぞれの立場や背景から語られる日常がやがてリンクしていく構成。ひとつの物語が終わるたびに、「次は誰の話だろう」と自然とページをめくってしまいます。
ラストに収められた「ココア」の章で、これまでの物語がやさしく結ばれていく瞬間は、思わず涙腺が緩んでしまうほどの温もり。短い時間で読めるのに、深く心に残る一冊です。
人魚が逃げた(青山美智子)
2025年の本屋大賞にもノミネートされた、青山美智子のやさしさが詰まった最新作。短編ごとに主人公が変わりながら、登場人物たちがゆるやかに繋がっていく連作形式で、読者を静かな感動へと導きます。
物語の中に登場するのは、人魚姫を探して旅をする王子様。おとぎ話のような存在が不思議と現実になじみ、登場人物たちの人生にそっと入り込んでいくことで、世界がほんの少し優しく変わっていきます。
誰かのささやかな行動が、めぐりめぐって別の誰かの希望になる。そんな青山さんならではの温もりが、全体をやさしく包み込む一冊です。日常に疲れたとき、そっと寄り添ってくれる物語を探している人におすすめです。
ツバキ文具店(小川糸著)
舞台は鎌倉にある、代筆屋を営む文具店。主人公は、依頼人の思いを受け取り、手紙を代わりに書く仕事をしています。離婚を決意した妻の一通、先生に想いを伝えたい小学生のラブレター、友情に終止符を打つ絶縁状――手紙に込められる感情の深さに、何度も胸が締めつけられます。
ペンの種類、紙の手触り、筆跡にまで心を配り、言葉にできない思いを丁寧に綴る姿がとても印象的です。物語のなかで実際に紹介される“代筆された手紙”もまた、小説の大きな魅力のひとつ。
主人公と、かつて厳しかった祖母との関係、近所に住む人々とのやりとりなど、登場人物たちの関係にも静かな優しさがあふれています。気持ちが疲れてしまったとき、そっと心を癒してくれる一冊です。
キラキラ共和国 (小川 糸著)
『ツバキ文具店』のその後を描いた、心あたたまる続編。舞台は引き続き鎌倉。代筆屋としての仕事を続けながら、主人公は少しずつ人との関わりを深め、静かに人生を歩んでいきます。
物語のなかで特に印象に残るのは、父子家庭のキューピーちゃんとそのお父さんとの交流。言葉にならない優しさや、寄り添うような気遣いが、日常の小さな場面にそっと散りばめられています。
のんびりとした鎌倉の空気とともに味わいたくなるような作品。派手な出来事はないけれど、読んだあと心がぽかぽかと温まるような余韻が残ります。前作を読んだ方にはもちろん、やさしい物語を求めているすべての人にすすめたい一冊です。
義経じゃないほうの源平合戦(白蔵盈太著)
源平合戦を描いた物語は数あれど、本作の主人公はあの義経でも頼朝でもなく、その兄・源範頼。義経の兄であり、頼朝の異母弟として歴史の陰に隠れがちな人物が、実は合戦の総大将として平家討伐の最前線にいた――そんな視点が新鮮で、物語をぐっと引き立てます。
兄・頼朝に対する畏れと、弟・義経への憧れ。二人の間に挟まれながら、範頼が感じる揺れ動く感情がとても人間的で、どこか切なくも温かい。時代小説でありながら、心理描写の丁寧さが心に残ります。
戦の中にも人間らしさが描かれていて、歴史の裏側にあったかもしれない“やさしい葛藤”を想像させてくれる一冊。歴史好きはもちろん、人の気持ちにじっくり触れたい読者にもおすすめです。
くちびるに歌を(中田英一著)
五島列島の中学校を舞台に、ひとりの美人音楽教師の赴任をきっかけに、合唱部に集まった思春期まっただ中の男子生徒たち。女子との距離感に戸惑いながら、同じ目標に向かって歌声を重ねていく日々が描かれます。
文化祭で披露するのは、アンジェラ・アキの「手紙 ~拝啓 十五の君へ~」。誰かに恋をして、告白のタイミングに胸を高鳴らせたり、ぎこちない会話に悩んだり。そんな中学生たちのまっすぐな気持ちに、思わず自分の昔を重ねてしまうような一冊です。
淡くて、優しくて、どこか懐かしい物語。成長の痛みや喜びが詰まった、青春小説の王道ともいえる作品です。
天国はまだ遠く(瀬尾まいこ著)
都会での生活に疲れ果て、生きることすら手放そうとしていた主人公がたどり着いたのは、日本海側の静かな村にある、ほとんど客の来ない古びた民宿。人生を終わらせるために訪れたその場所で、少しずつ変化が訪れます。
ぶっきらぼうだけどあたたかい民宿の兄ちゃんや、のんびりとした地元の人たちとのやりとり、素朴で滋味あふれるごはん。何気ない日々のなかで、張りつめていた心がゆっくりほぐれていく様子が丁寧に描かれます。
派手な展開はないけれど、静かで深い余韻を残す一冊。自分を見失いかけたときに読みたくなる、やさしさに満ちた物語です。
日常の中に優しさを見つける「ほっこり系ストーリー」
慌ただしい毎日や、心がちょっと疲れた日。そんな時にそっと寄り添ってくれるのが、日常の中にあるやさしさや、人と人とのあたたかなつながりを描いた“ほっこり系”の物語です。
大きな事件はなくても、静かに心がほぐれて、気づけば少し笑っていて、読み終えたあとには、世界がほんの少しやさしく見えてくる。そんな作品を集めました。
かもめ食堂(群ようこ)
舞台はフィンランド・ヘルシンキ。日本人女性が営む小さな食堂「かもめ食堂」に、ふとしたきっかけで人が集まり、少しずつ人間関係が広がっていきます。特別な事件は起きないけれど、静かであたたかな時間がそこには流れています。
まったく異なる人生を歩んできた登場人物たちが、この食堂を拠点にゆるやかにつながっていく様子は、人生の“偶然”や“流れ”をそっと肯定してくれるようです。
読んでいると、シナモンロールの香りや森の空気まで感じられるようで、慌ただしい日常から少し距離を置きたくなります。もっと優しく、ゆっくりと生きてみようと思わせてくれる一冊です。
店長がいっぱい(山本幸久著)
丼ものチェーン「友々屋」の各店舗で働く店長たちが、それぞれ主人公となって描かれる連作短編集。1話ごとに店が変わり、登場人物も入れ替わりながら、ユーモアと人情味に満ちた日常が語られます。
接客の悩み、部下との関係、家庭との両立…。どの店長にも、それぞれの事情があり、それぞれの物語があります。誰かの立場に立ってみることで「人はみんな頑張ってるんだな」と自然と優しい気持ちになれる一冊。
肩肘張らずに読めて、ホッとする読後感。気づけば笑っていて、最後にはちょっと泣けてくる。毎日がちょっとしんどいと感じたとき、そっと背中を押してくれるような作品です。
夜のピクニック(恩田陸著)
高校生活のラストを飾る伝統行事「24時間歩行祭」。ただひたすら夜通し歩き続けるだけのイベントに、生徒たちはそれぞれの思いや願いを抱えて臨みます。そんな一夜の物語を、瑞々しく描いた青春小説です。
学生時代の独特な空気、どうしようもない気恥ずかしさやまっすぐな感情がよみがえり、読みながら「もう一度戻りたい」と「もう戻りたくない」が心の中でせめぎ合う、不思議な読後感。
大人になった今だからこそ沁みる言葉も多く、若い人たちには“今”を大切にしてほしいと、素直に思わされます。静かに心が揺れる、優しくて、どこか切ない一冊です。
つむじ風食堂の夜(吉田篤弘著)
どこか懐かしくて優しい空気が流れる月舟町の食堂を舞台に、静かであたたかな人間模様が紡がれる連作短編集。登場人物はみな善良で、穏やかで、読んでいるうちに自然と心がほぐれていきます。
大きな事件やどんでん返しはありません。ただ日常の中にある、ささやかな温もりと少しの不思議。心拍数が上がるような展開はなくても、読後にはじんわりと満ちる安心感があります。
章末に添えられる一文がどれも味わい深く、「次の電車の一番乗りになれる」という言葉には、日々の焦りをそっとほどいてもらえるような優しさが。慌ただしい日常から離れ、静かな読書時間を過ごしたいときにおすすめです。
ランチのアッコちゃん(柚木麻子著)
とにかく読後、前向きな気持ちになれる短編集。ひとクセもふたクセもあるけれど、どこか憎めない登場人物たちの奮闘が描かれています。
タイトルにもなっているアッコさんは豪快で頼もしい先輩女性。彼女の“移動デリ”で提供される「東京ポトフ」がとにかく美味しそうで、お腹まで空いてくるのもこの本の魅力です。仕事で落ち込んだとき、何だかうまくいかないとき、ふと手に取って読み返したくなる一冊。し
阪急電車(有川浩)
阪急電車に乗ったことがある人はもちろん、関西にゆかりのある方ならきっと胸に響く優しい物語。舞台は、阪急今津線。各駅ごとに異なる登場人物のドラマが描かれ、車内で交差する人生が、少しずつリンクしていきます。
あずき色の車体、落ち着いた内装、どこか懐かしい車内の空気まで小説から伝わってくるようで、「ああ、阪急電車に乗りたい」と思わせてくれます。特急レイアウトの京都線で読めたら最高かも。
偶然のすれ違いや小さな気づきが、誰かの人生をそっと変えていく。人の温かさや日常の奇跡を、丁寧に描いた一冊です。移動時間に読むのにもぴったりな、ほっこり優しい小説。
食堂かたつむり(小川糸著)
恋に破れ、声まで失った主人公が故郷に戻って開いたのは、1日1組限定の小さな食堂。地元の食材を丁寧に使い、筆談でおもてなしをするその料理には、不思議な力が宿っています。
インド人の恋人にすべてを奪われた直後の再出発。都会を離れ、静かな町で始まる新しい生活のなかで、少しずつ心が癒されていく様子に、読む側の心もじんわりと温かくなります。
何よりも料理の描写が絶品で、お腹がすいてしまうのが唯一の注意点。優しさと再生、そして小さな奇跡が詰まった、ほっこりと泣ける物語です。
ミラクル(辻仁成著)
親を亡くした少年が主人公の、静かで心に染みる物語。子ども向けと思われがちですが、大人の心にもそっと寄り添ってくれる、やさしさに満ちた一冊です。
物語の終盤に訪れる“ミラクル”の場面では、登場人物それぞれの想いを想像するだけで胸が熱くなり、自然と涙がこぼれてしまいました。読後に残るのは、穏やかであたたかな気持ち。重いテーマを扱いながらも、辻仁成さんの“人の痛みに寄り添う力”が感じられる、小さな奇跡のような感動小説です。
短時間で感動できる「泣ける&優しい短編集」
忙しい日々のすき間時間に、そっと心を潤してくれる短編集を集めました。
どれも短い物語なのに、不思議と涙がにじんだり、あたたかい気持ちになったり。
日常のささやかな瞬間や、誰かのやさしさが胸に残る――そんな作品ばかりです。
ほんの数ページで、思わず涙ぐんでしまうことも。
静かに泣きたい夜、気持ちを切り替えたいときにおすすめです。
<あの絵>のまえで(原田マハ著)
美術を愛するすべての人に読んでほしい、心にしみる短編集。名画にまつわる5つの物語が、やさしく、そして静かに心を揺さぶります。
中でも印象深いのは、夢破れた女性が祖母に似た隣人との交流を通して再び前を向く「豊饒」。表紙に描かれたクリムトの同名作品と響き合い、物語の余韻をいっそう深めてくれます。どのお話も美術館にいるような静けさとあたたかさが漂い、電車の中で思わず涙をこらえたくなるような場面も。
原田マハさんならではの美術への眼差しと、人の心を描くやさしい筆致が詰まった、感動の一冊です。読み終えた後には、きっと絵がもっと好きになっているはず。
昨夜のカレー、明日のパン(木皿泉著)
大切な人を亡くした喪失の中で、それでも笑ったり、ごはんを食べたりしながら少しずつ日常を取り戻していく人たちの姿を描いた、やさしい再生の物語。
夫を亡くした女性と、義父との不思議であたたかな同居生活。カレーを作った翌日に少しだけ笑えるような、そんな小さな希望が散りばめられています。
タイトルからは想像できないほど深くて優しい「泣ける小説」。悲しみの中にある微笑みや、日々の暮らしの愛おしさがじんわりと心に沁みます。読後には、今日のごはんを少し丁寧に作ってみたくなるかもしれません。2日目のカレーはコクが出てめっちゃ美味しい!みたいな話だと思っていた自分をグーで殴りたいです。
独立記念日(原田マハ著)
女性たちの小さな一歩と大きな決意を描いた、やさしくも力強い24の短編集。日常のささやかな出来事を通して、それぞれの「独立」の物語がゆるやかに交差していきます。
特に後半の「ひなたを歩こう」から「川面をわたる風」へと続く展開は圧巻で、読んでいて自然と涙がこぼれました。ときに切なく、ときにあたたかく、心をそっと後押ししてくれる一冊です。
読み終えたあと、もう一度最初から読み返したくなる構成も魅力。優しい気持ちになりたいときに、そっと寄り添ってくれる「感動小説」です。
最後に
泣ける小説、感動する物語、優しい気持ちになれる本。
どれも読んだあとに「読んでよかったなあ」としみじみ思える一冊ばかりです。
忙しい毎日、ちょっと疲れたときや元気が出ないとき、ふと誰かに優しくしてもらいたいなって思ったとき。
そんなときこそ、こういう物語がじんわりと心に効きます。
もし気になる本があったら、ぜひ読んでみてください。
きっと、あなたの気持ちにそっと寄り添ってくれるはずです。
-
【2025年版】泣ける・感動・優しい小説おすすめ43選|心を癒す名作を厳選
-
元気が出る&前向きになれる小説24選|落ち込んだ日にそっと寄り添う本
-
【2025年最新版】どんでん返し小説123選|衝撃のラストに驚くミステリー本まとめ
-
【最速!10秒でネタバレ】どんでん返し小説『看守の流儀』
-
【2025年版】読みやすくて面白いノンフィクション・エッセイ27選
-
【10秒ネタバレ】閲覧厳禁!どんでん返し・ミステリー小説32冊
-
【2025年版】短編小説おすすめ34選|就寝前・通勤中に読める名作集
-
【2025年版】テンションが上がり、熱くなれる!おすすめ小説17選
-
【2025年版】原田マハのおすすめ小説8選|初めてでも感動できる名作を厳選紹介
-
【2025年版】読書家が選ぶ歴史小説おすすめ22選|時代を超えて心に残る名作・傑作集


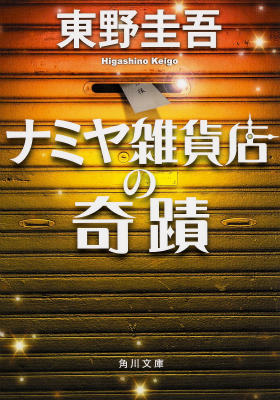
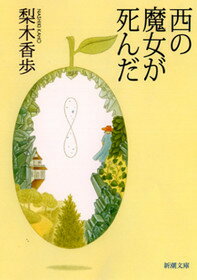
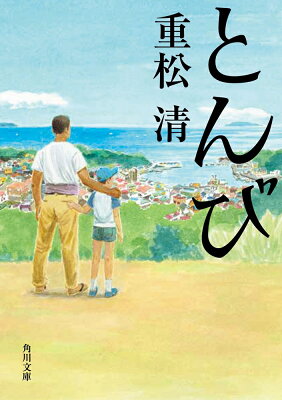
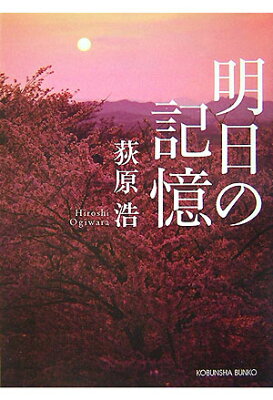



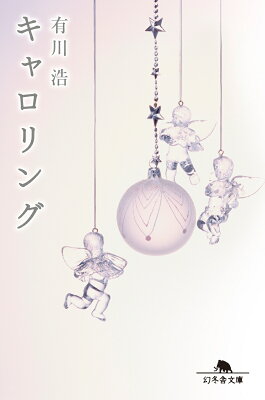





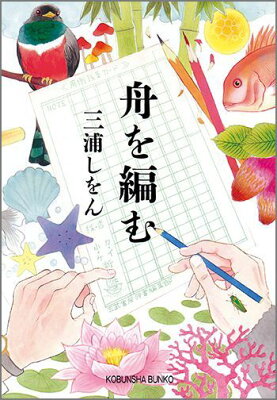


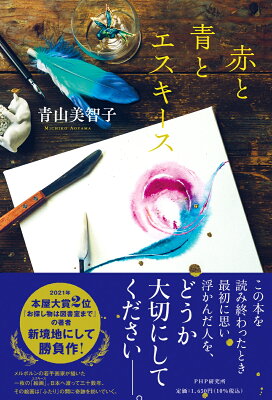

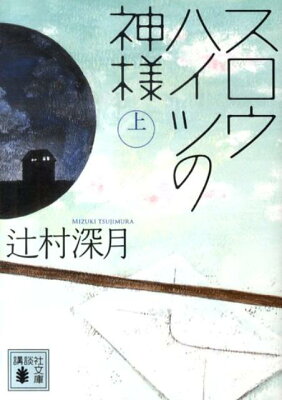

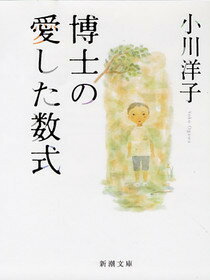













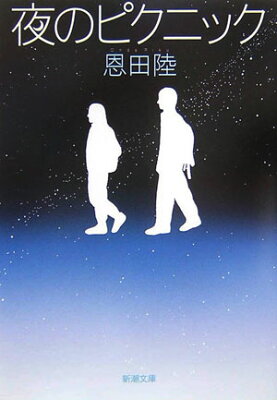


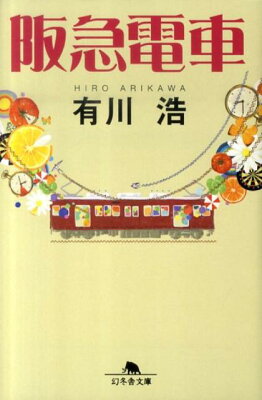
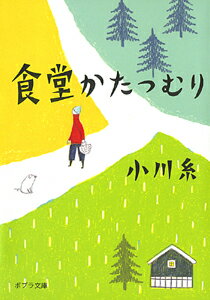


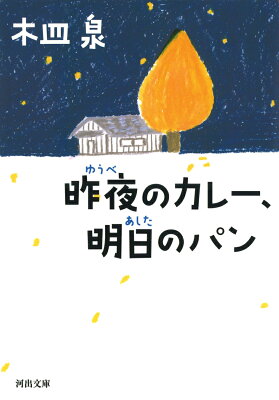

コメント